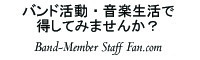>メンバーを知ればバンドが成長する 簡単な知識が大きな成功に
Vol.1 バンドはひとりじゃない
バンドはひとりではありません。
複数の人間のコミュニケーションです。
複数の音のコミュニケーションと言ったほうがかっこいいでしょうか?
たとえばバンドで演奏するにしても、
メンバーそれぞれが自分のパートの楽譜をもらってきてそのとおりに演奏し、
ほかのメンバーに全く干渉しないということはありません。
もちろん楽器をはじめて最初のころは自分のことで精一杯でほかのメンバーに対してなにも助言できないということはあります。
しかしほかのメンバーと意見を言いあってバンドが良くなっていくのです。
たとえばバンドで練習するとき、それは自分のための練習でもありますが
メンバーどうしの意見交換の場でもあります。
自分のパート以外はそのパートのメンバーに完全にお任せというのではなく、
お互いに「○○をどうしたほうがいい」などと意見を出しあって、もっとよい音楽を作っていくのです。
そのために、ほかのメンバーが担当する楽器であっても、
知識があるのとないのとでは意見交換のしやすさがずいぶんと違ってきます。
最低限の知識があるだけでバンドのコミュニケーションがとれたり活動がうまくいったりするのです。
これらの知識をまず最初に身につけて
バンドでコミュニケーションをとり、もっともっといい音楽を作っていきましょう。
もしもあなたがバンドを組んだ経験がないのなら、
バンドのメンバーを探しながらでも、ほかのパートの知識を身につけてしまいましょう。
メンバー募集ではじめて会った人とも、もっと深く話をすることができるかもしれません。
このサイトでは、バンドでよく使われている、ヴォーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードの基本的な知識を説明していきます。
あなたもほかのパートの知識を増やしてコミュニケーションをとりましょう。
きっと今まで以上にバンドがうまくいくはずですよ。
Vol.2 バンドの構成
バンドの構成についてコミュニケーションをとってみましょう。
まずは人数を表す言葉です。
シングル
1人という意味です。
バンドの構成の場合では、そのパートのメンバーが1人だけという意味になります。
たとえばギターが1人だけの場合、シングルギターといいます。
「ウチのバンド、ギターはシングルです」といえば、バンドの構成でギターは1人だけという意味になります。
ツイン
2人という意味です。
バンドの構成の場合では、そのパートのメンバーが2人いるという意味になります。
たとえばギターが2人いる場合、ツインギターといいます。
「ウチのバンド、ギターはツインです」といえば、バンドの構成でギターが2人いるという意味になります。
ツインギターに限らず、ツインヴォーカルのバンドもいれば、ツインベースのバンドもいますね。
では、ツインギターのバンドを考えてみましょう。
2人いるのですから、2人ともまったく同じフレーズを弾くのではなく、
それぞれ役割分担をしているはずです。
そこで、役割によって呼ばれ方があります。
リードギター
曲の主旋律を受けもつギターをいいます。
つまり、ツインギターのうち、おもにソロなどの単音弾きを担当するギターです。
とても目立つパートですのでヴォーカル同様にバンドの顔といえます。
ですから、バンド活動が活発になってくれば、個性や人をひきつける能力が問われることも多くなります。
サイドギター
ツインギターのうち、おもにコード弾きなどでリズムを担当するギターをいいます。
リードギターとくらべると、演出的には少し地味かもしれません。
初心者の方はよく「リードギターは難しそうだからサイドギターがやりたい」などのようにいいます。
誤解されがちなのですが、サイドギターはリズム側を担当しているぶん、
リードギターよりもしっかりとした音が求められることが多いのです。
ツインリード
ツインギターで、2人ともリードギターの役割をすることをいいます。
主旋律が2本ということになりますので、アレンジ能力が高くないとなかなかうまくいきません。
かなりのアレンジ経験を積んだ人でない限り、
リードギターとサイドギターでしっかりと役割分担したほうがバンドがまとまります。
リードとサイドという言葉が出ました。
ギター以外にもリードとサイドという言葉は使われます。
リードヴォーカル
主旋律を受けもつヴォーカルをいいます。
普通にヴォーカルと言うことのほうが多いのですが、
歌う人が何人もいるようなグループでは役割分担をすることが多いので、
そういった場合にリードヴォーカルという表現をします。
また、曲の途中でギターなどのほかのメンバーが部分的に歌うこともあるでしょう。
そういったものと区別する意味合いでリードヴォーカルと呼ばれます。
コーラス
リードヴォーカル以外のヴォーカルをコーラスといいます。
歌う人が何人もいるようなグループでは、リードヴォーカル以外はコーラスといい、
曲の途中でギターなどのほかのメンバーが部分的に歌うような場合もコーラスといいます。
では、ツインギターの話にもどしましょう。
ギターの音の役割ではなく、ライヴなどの立ち位置でギターを呼び分けることもあります。
では、立ち位置の用語とまじえて紹介します。
センター
英語の「center」です。
これの意味は「中央」です。
ステージの中央という意味でセンターという言葉を使います。
ヴォーカルが何人もいるようなグループの場合、
ステージ中央のヴォーカルをセンターヴォーカルといいます。
また、中心となっているヴォーカルという意味からもセンターヴォーカルといいます。
上手(かみて)
客席からステージを見たときに、ステージの右側のことをいいます。
ツインギターのバンドで、上手側のギターを上手ギターといいます。
下手(しもて)
客席からステージを見たときに、ステージの左側のことをいいます。
ツインギターのバンドで、下手側のギターを下手ギターといいます。
ではバンド内のメンバー数人を、機能ごとにまとめて呼び分けてみましょう。
楽器隊
バンドの中で、楽器を弾く人をまとめて楽器隊といいます。
ほとんどのバンドでは、ヴォーカル以外は全員、楽器隊ということになります。
コーラス専門のメンバーやダンサーなどは楽器隊には含まれません。
リズム隊
ドラムとベースのことをいいます。
考え方によっては、リズムを担当するサイドギターも、リズム隊に含まれることがあります。
フロント
ライヴをする際の立ち位置が、ステージの前方のメンバーをいいます。
一般的にはドラム以外のメンバー全員をいいます。
しかし、常にステージの後方で演奏しているメンバーはフロントといいません。
たとえば、キーボードは立ち位置を変えることができません。
そこで、キーボードがステージの前方に配置されていたらフロントと呼び、
ステージの後方に配置されていたらフロントとは呼びません。
Vol.3 機材・備品の基礎知識
機材・備品の基礎知識を身につけましょう。
まずはヴォーカルで使う機材です。
ヴォーカルで使う機材でいちばんに思いつくのはマイクですね。
しかし、マイクとはいっても、マイクには種類があります。

ダイナミックマイク
よくライヴなどで使われている一般的なマイクです。
価格も安く、ある程度は丈夫にできています。
コンデンサーマイク
コンデンサーマイクがダイナミックマイクと違うのは、電源をつながなければならないことです。
一般の人の場合、ほとんど見る機会がないと思います。
コンデンサーマイクは、音を繊細に拾うことができるので、よくレコーディングに使われます。
高価で、最低でも2万円くらいはします。
また、湿気や振動に弱いので、保管が大変です。
うっかり落としてしまっただけで壊れることもあり、高価な機材だけに注意が必要です。
ワイヤレスマイク
ミキサーやアンプなどにつなぐケーブルが必要のないマイクです。
ワイヤレスマイクから電波を出し、それを別の機材で受け取ります。
電波を受け取る機材をレシーバーといい、レシーバーをミキサーやアンプなどにつなぐのです。
つまり、ワイヤレスマイクからレシーバーの間だけ、接続するコードがいらなくなるのです。
ワイヤレスマイクはライヴでは非常に便利です。
コードが足に引っかかることもないので、パフォーマンスも幅も広がるでしょう。
しかし、音が悪くなるという欠点があります。
ギターやベースでもワイヤレスは使われますが、
ヴォーカルのワイヤレスマイクが特に音の劣化が大きいように思われます。
ライヴハウスのスタッフに話を聞いてみると、バンドマンには気を使って言わないのでしょうが、
実際にはヴォーカルがワイヤレスマイクを使うことを嫌がっていたりします。(・o・;)
ヴォーカルで使うのはマイク本体だけではありませんね?
では、備品について、最低限、知っておきたいものだけ紹介します。
スタンド
マイクスタンドです。
マイクを立てる金属棒ですね。
略してスタンドということも多いです。

キャノン
おもにマイクとつなぐために使われるケーブルです。
ケーブル自体はシールドに似ていますが、端の部分に特徴があります。

このタイプのケーブルをキャノンケーブルといいますが、略してキャノンということも多いです。
では、ギターやベースの機材を見ていきましょう。
まずはギター本体ですね。
ギターにもいろいろな種類があります。
エレキ
おなじみのエレキギターです。

普通、バンドをやっていてギターといえばエレキギターで通じるのですが、
複数の種類のギターを使い分けるときには、それらと区別する目的でエレキということもあります。
アコギ / エレアコ
アコースティックギターのことを短縮してこう呼びます。
また、エレキのアコースティックギターのことをエレアコといいます。
では、次はベースです。
ベース
今では5弦や6弦のベースが当たり前のようにありますが
一般的にベースの弦は4本ですね。
単純にギターの弦が4本になったのではなく、音の高さが違っています。

次は備品を紹介します。
まず、ギターやベースを弾くときには・・・
ピック
ギターやベースを弾くための道具ですね。
もちろん指で弾くこともできますが。

ピックには硬さがあります。
硬いピックほど、弾いたときのアタック音がしっかりと出ます。
いい音を出すためには硬いピックを使いたいところです。
そのぶん、しっかりと握っていなければなりません。
やわらかいピックの場合、弾いたときのアタック音が少なくなります。
そのため、オモチャっぽい音になってしまいがちです。
やわらかいピックのメリットとしては、
力を入れなくてもピックがしなることによって弦をはじき、音を出してくれることです。
よけいな力がかからないぶん、弦が切れにくくなります。
また、やわらかいピックのほうが弾きやすいという人も多いようです。
シールド
ギターやベースとアンプをつなぐコードのことです。

シールドの質によって、音が全然違ってきます。
ギターやベースを買ったときにオマケでつけてくれるシールドや安く売られているシールドではなく、
できれば良いシールドを使いたいところです。
ストラップ
ギターやベースを肩からつりさげるための肩ひものことです。
いろいろなデザインのストラップが売られていますね。
チューナー
弦の音程をあわせることをチューニングといいます。
そしてチューニングをするために、鳴っている音の高さを調べる機械を
チューニングメーター、またはチューナーといいます。

音叉(おんさ)という金属棒を使ってチューニングをする人もいます。
音叉とは、共振を利用して弦の音程を合わせるための金属棒です。
大音量で鳴らすためにはアンプが必要ですね。
もちろん大音量とまではいかなくても、生の音ではなく機械を通した音を出したいときにはアンプが必要です。
アンプとは音を増幅させる機材のことですが、アンプにも種類があります。
パワーアンプ
最終的に出される音にまで増幅させるアンプをいいます。
つまり、最終的な音量はパワーアンプによって決められるのです。
プリアンプ
「pre (プリ)」とは、「前、先、あらかじめ」などの意味があります。
パワーアンプで音を増幅させるより前に、段階的に少しだけ音を増幅させる機材をいいます。
また、プリアンプとパワーアンプが一体となったものもあります。
ひとつの機材にプリアンプとパワーアンプの両方が入っているのです。
プリアンプは省略してプリということもあります。
バンドマンがプリといったらプリアンプです。
プリクラではないですよ。
キャビ
これはキャビネットの略です。
簡単に言ってしまうとスピーカーのことです。
一般的にアンプといったら、パワーアンプ、またはパワーアンプとプリアンプの一体型のことをいいます。
キャビネットはアンプではありません。
機材によってはアンプとキャビが一体となっているものもあります。
このように、アンプとスピーカー部分が一体となったタイプのものをビルト・インといいます。
逆に、アンプとキャビネットを積み重ねて使うことをスタックといいます
次はドラムにいきましょう。
ドラムにはいくつもの太鼓などがあります。
いくつもの太鼓などがセットになって、ドラム、ドラムセットといいます。
そして、それぞれに名前がついています。
バスドラ
これは正面下にある、足を使ってたたくいちばん大きな太鼓です。
正しくはバスドラムですが、ちょっとだけ短縮してバスドラといいます。
バスドラムはベードラと呼ばれることもあります。
バスドラムは、バンドによって1個だけだったり、2個使っていたりします。
ワンバス
バスドラムが1つという意味です。
一般的にはワンバスです。
ツーバス
バスドラムが2つという意味です。
右足と左足の両方でたたくので、単純に考えたら音の数は2倍になります。
激しい曲をやっているバンドに多いようです。
スネア
イスに座ったときに正面手前に置かれているドラムです。
スネアとは、太鼓の下側の面に張られている金属の弦のことをいい、それがつけられているドラムなので、スネアドラムです。
ほとんどの場合、スネア・ドラムを短縮して「スネア」と言ってしまいます。
ドラムが自分の楽器といったら、このスネアドラムのことです。
自分の楽器なのですから、もちろん持っていなければなりません。
スタジオでは借りることができますが、ライヴハウスでは貸してくれないところも多いです。
タム
正面奥に取りつけられているドラムです。
タムは1個だけではなく2個や3個の場合もあり、
このような場合、音が低いほうから順にタム、タムタム、タムタムタムなどのようにいいます。
フロア
フロア・タムを省略してフロアといいます。
床置きタイプのドラムで、ふつうタムよりも低い音がでます。
ハット
ハイハットを省略してハットといいます。
2枚の小さなシンバルではさみこむ形をしているもので、ペダルがついています。
カウントをとったり、リズムを刻んだりするのによく使われます。
3点セット
バスドラム、スネア、ハイハットの3つをまとめて3点セットといいます。
この3つがドラムの基本になっています。
○タム○フロアー
ドラムセットを聞かれたときに「ツータム・ワンフロアー(タムが2個でフロアーが1個)です」などのように答えます。
もちろんドラムセットがそれだけというのではなく「3点セットにプラスして」という意味になります。
3点セットは誰もが使うものですから、それ以外に何を使うかを答えればいいのです。
ではドラムの備品を紹介します。
スティック
ドラムをたたくための木の棒です。
様々な太さのスティックが売られています。
たたいているうちに折れてしまうことも多いので、予備にかならず2セット(4本)くらいは持っていたいところです。
ペダル
足で踏んでバスドラムをたたくための道具です。
これは備品や機材というよりはドラムの体の一部ですので、
できる限り早く買った方がいいでしょう。
ツーバスであればペダルは2個必要です。
ツインペダル
ペダルが2個で1セットになったものです。
左右の足でペダルを踏み、1つのバスドラムをたたきます。
両足で踏むので、たたくことができる数はツーバスと同じになるのですが、
音はツーバスとは違ってきます。
また、機材の名前ではなく、ワンバスでペダルだけ2個つけてある状態をツインペダルということもあります。
チューニングキー
太鼓の皮の張り具合を調節するための小道具です。
弦楽器のように決まった音の高さに合わせるのではなく、
自分の好きな音になるように調節します。
では最後にキーボードの機材です。
シンセ
シンセサイザーの略です。
電気的に音を合成する装置をいいます。
音源
キーボードやDTMなどで出すことができるさまざまな音色が入った機材、または音色プログラムをいいます。
キーボード弾いたものやパソコンで入力したものがそのまま音になるのではなく、
音源を通して音色が決められ、その音を発音しています。
正式には音源モジュールといいます。
音源モジュールを短縮して「音源」ということも多いです。
発音させる音やタイミングなどはMIDIデータでやり取りさせるので、MIDI音源と呼ばれることも多いです。

多くのキーボードやパソコンでは音源が内蔵されていますが、外付けすることもできます。
ですから、好きな音の音源だけ別に買ってきて、キーボードとつなげて使うこともできます。
エレピ
エレクトリックピアノの略です。
電子ピアノのことです。
サンプラー
生の音をデジタル録音し、それを加工したり音程をつけたりして、音源として使う機材をいいます。
生の音をデジタル信号化して録音することを「サンプリング」といいます。
マイクで録った楽器の音、CDなどの音、自然の音、日常の生活音など、様々な音をサンプリングして利用します。
RCA
そのままアールシーエーと読みます。
赤と白の2本が1束になったケーブルのことです。

MIDI
ミディと読みます。
キーボードと外部の音源を接続するときの信号のやり取りの規格です。
そして、MIDI信号をつたえるケーブルをMIDIケーブルといいます。
MIDIケーブルは5本足のジャックになっています。