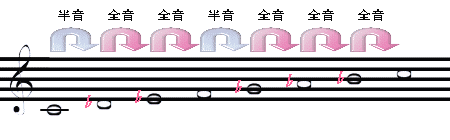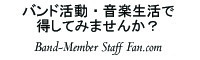>旋律論
Vol.1 幹音とオクターブ
鍵盤には、手前に白の白鍵(はっけん)と、これよりも奥に黒の黒鍵(こっけん)の2種類があります。
白鍵にならんでいる音は音名を言うときに基礎になる音なので幹音(かんおん)といいます。
幹音はC・D・E・F・G・A・Bというようにならび方が決まっています。
この幹音のならびを、幹音列(かんおんれつ)といいます。
また、黒鍵では幹音と幹音の間の音をあらわす事ができます。
五つの黒鍵の出す音を派生音(はせいおん)といいます。
まずは、白鍵と黒鍵の組み合わせ方を覚えてしまいましょう。
黒鍵は、二つ、または三つが並んで一組となって交互に出てきています。
二つ並んだ黒鍵の左側の白鍵は、常にC(ハ・Do)の音になっています。
そして、その音から順に右の方に向かって、D、E、F、G、A、Bとなっています。
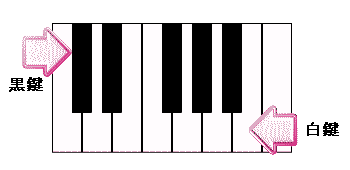
楽音は、七つの幹音を1組として、それよりも高い方、低い方へ何組でも繰り返して並べられています。
それぞれの幹音は一定の間隔を置いて、高低のどちらへも繰り返して現れることになります。
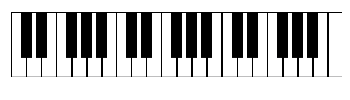
あるひとつの幹音から数えて、上または下に8番目のところに、再び同じ音名をもった音が現れます。
このように同じ音名を持ち、違う高さを持つ二つの音の間隔をオクターブ/octaveといいます。
オクターブとは八度音程のことです。
オクターブの間隔が2つ分以上のとき、八度音程のオクターブと区別して、2オクターブ、3オクターブ…といいます。
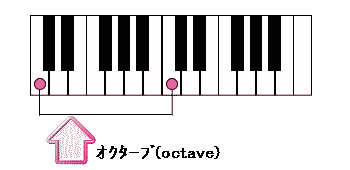
下の図のように、ハ音から始まりロ音までの各組を、
ひらがな、カタカナ、点などを用いることにより、音の高低(オクターブ)を表します。
たとえば、カタカナハ音のオクターブ下を「は」と書き表し、「ひらがなハ音」といいます。
さらにオクターブ下を「下一点ハ音」といい、「は」の下に「・」を一つ付けて書き表します。
また、カタカナハ音のオクターブ上を「一点ハ音」といい、「ハ」の上に「・」を一つ付けます。
さらに上に行くと「ニ点ハ音」、「三点ハ音」と上がっていき、「ハ」の上に「・」をニつ、三つ、と増やしていきます。
また、一点音からなる音名の集合を「一点オクターブ」と呼びます。
同じように、ひらがな音、カタカナ音などの集合を、「ひらがなオクターブ」、「カタカナオクターブ」などと、
それぞれに名前が付けられます。
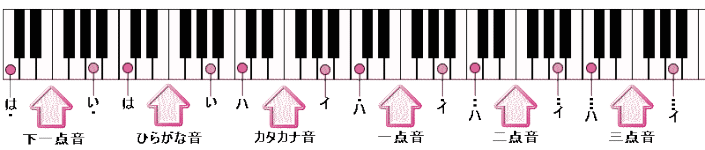
オクターブの表記のしかたは各国によって違います。
ドイツ、米・英では、ひらがな音をアルファベットの大文字で、カタカナ音をアルファベットの小文字で表記します。
それより上、または下の音については下の表を参考にしてください。
各国2種類の表記法があります。
| 日本 | 下二点音 | 下一点音 | 平仮名音 | 片仮名音 | 一点音 | 二点音 |
い : |
は ・ |
は | ハ | ・ ハ |
: ハ |
|
| ドイツ | 2A | 1C | C | c | c1 | c2 |
A = |
C - |
C | c | _ c |
= c |
|
| 米・英 | A2 | C1 | C | c | c' | c" |
| AAA | CC | C | c | c1 | c2 |
これらのオクターブの表記などをするとき、ある高度を基準にして名前がつけられていきます。
この基準となる高度を紹介します。
① 一点イ音(標準高度)
一点イ音の高度(こうど)、(ピッチ/pitch)は、1秒間に435回の振動数(435Hz)と定められ、
これを楽音を調律するときの国際的な基準音としました。
これを標準高度、または、国際高度といいます。
しかし、実際に演奏をする際には、
標準高度とは異なる高度(演奏高度:演奏をする時の基準となる高度)を用いて調律することが多くなり、
それらを理由に標準高度は改正され、現在では440Hzを新しい標準高度と定められました。
② 一点ハ音(中央ハ音)
一点ハ音は、楽音で使われる全音域のほぼ中央にあたり、
楽譜においても、高音部と低音部のちょうど中央に位置しています。
そのため、一点ハ音は中央ハ音(センターC/center C)といいます。
振動数は261.6Hzになります。
鍵盤では隣同士であっても、音程の間隔が常に一定というわけではありません。
音程の間隔には全音と半音があります。
ひとつの黒鍵をはさんだ幹音と幹音の音程の間隔を全音(ぜんおん)といいます。
これに対して、黒鍵をはさまない幹音と幹音の音程の間隔を半音(はんおん)といいます。
また、黒鍵とそれに隣接する幹音との音程の間隔も半音になります。
全音は半音の2倍の間隔になっています。
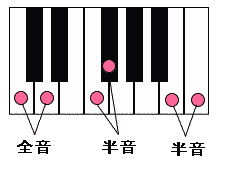
鍵盤には、幹音である白鍵のほかに、黒鍵が存在しています。
この黒鍵にあたるのが派生音(はせいおん)です。
Vol.2 派生音の種類
① 嬰記号と嬰種派生音
ある幹音をもとにして、半音高い音を嬰種派生音(えいしゅはせいおん)といい、
もとになる幹音名の後に♯を付けてA♯などのように呼びます。
譜表の上では幹音の符頭の左側に「♯」の記号を付けて表します。
この「♯」記号はシャープ/sharpと読み、日本では嬰記号(えいきごう)と呼ばれます。
鍵盤では幹音の右の黒鍵が嬰種派生音にあたります。
もしも右に黒鍵がない場合は、右隣の白鍵が嬰種派生音にあたります。
日本での嬰種派生音の音名の言い方は、もとになる幹音名の前に「嬰」の文字を付けて嬰イ音などのように呼びます。
② 変記号と変種派生音
ある幹音をもとにして、半音低い音を変種派生音(へんしゅはせいおん)といい、
もとになる幹音名の後に♭を付けてA♭などのように呼びます。
譜表の上では、幹音の符頭の左側に「♭」の記号を付けて表します。
この「♭」記号はフラット/flatと読み、日本では変記号(へんきごう)と呼ばれます。
鍵盤では幹音の左の黒鍵が変種派生音にあたります。
もしも左に黒鍵がない場合は、左隣の白鍵が変種派生音にあたります。
日本での変種派生音の音名の言い方は、もとになる幹音名の前に「変」の文字を付けて変イ音などのように呼びます。
③ 重嬰記号
嬰種派生音よりもさらに半音高い音をダブルシャープで表すことができます。
日本では嬰種派生音に「重」の文字を付けて重嬰イ音などのように呼びます。
譜表の上では、幹音の符頭の左側に「
この「
④ 重変記号
同じように、変種派生音よりもさらに半音低い音はダブルフラットで表すことができます。
変種派生音に「重」の文字を付けて重変イ音などのように呼びます。
譜表の上では、幹音の符頭の左側に「
この「
<各国の派生音の呼び方>
| ♯ | ♭ | ||||
| 日本 | 記述 | 嬰 | 重嬰 | 変 | 重変 |
| 米・英 | 記述 | sharp | doubre sharp | flat | doubre flat |
| 読み方 | シャープ | ダブルシャープ | フラット | ダブルフラット | |
| ドイツ | 記述 | is | isis | ces | eces |
| 読み方 | イス | イシス | エス | エセス | |
| フランス | 記述 | diese | doubre diese | bemol | doubre bemol |
| 読み方 | ディエーズ | ドゥブルディエーズ | ベモル | ドゥブルベモル | |
| イタリア | 記述 | diesis | doppio diesis | bemolle | doppio bemolle |
| 読み方 | ディエジス | ドッピオディエジス | ベモーレ | ドッピオベモーレ | |
⑤ 本位記号と本位音
変化記号によって変化した音をもとの高さの音にもどす場合、符頭の左側に「
この「
また、これによってもとの高さにもどされた音を本位音(ほんいおん)といいます。
重嬰記号・重変記号の付いた音から幹音にもどす場合、同様に「
重嬰記号・重変記号の付いた音から嬰記号・変記号の付いた音に変化させる場合、嬰記号・変記号を付けるだけです。
「
では、これらの記号の使い方についてです。
嬰記号と変記号は、幹音の高さと性質を変化させるものであるので、これらは変化記号(へんかきごう)とも呼ばれます。
本位記号も変化記号に含まれます。
これらの記号が楽曲の最初(音部記号の右側)に付けられた場合、楽曲全体の同じ高さの音すべてに影響します。
この場合、楽曲の調を表しているため、これらの記号は調号(ちょうごう)と呼ばれます。
調号による嬰記号と変記号は、それらのしめす音の高さのほかにオクターブ違いの音にも影響します。
また、これらが、楽曲中で臨時に使用される場合、これを臨時記号(りんじきごう)といいます。
この場合、変化記号は変化記号の付いた音より後に出てくる同一小節内にある同じ高さの音すべてに影響します。
ですから、同一小節内の同じ高さの音に変化記号を付けたい場合、先に出てきた音符に1つだけ付ければよいことになります。
ただし和音の場合、そのたびに変化記号を付けた方がよいとされています。
臨時記号の影響範囲は同一小節内だけなので、次の小節からは、もとに(調号の通りに)もどることになります。
オクターブ違いの音が、臨時記号によって影響されるかどうかは、
オクターブ音に、♯・♭・
つまり、臨時記号として部分的に♯・♭・
そのオクターブ音は♯・♭・
臨時記号は、その小節内の音符から、タイ記号で連結されている音符に限り小節をまたいでも効果が継続します。
このタイ記号で連結した音符の後に、再び音程変化をさせたい音符については、
あらためて、♯・♭を記入しなければなりません。
A♯とB♭は、鍵盤上では同じ位置を示しています。
また、A
これ以外にも音名の呼び名や譜表上での表記方法が異なっていながら、実際には同じ音高を表すものがあります。
こういった場合、これらの2つの音を異名同音(いめいどうおん)といいます。
これを用いて、ある音の呼び方や譜表上の書き方を異名同音のものに置き換えることができます。
こうして置き換えることを、異名同音的転換(いめいどうおんてきてんかん)といいます。
幹音に嬰派生音・変派生音を含めた全ての楽音の音程の間隔を定めたものを音律(おんりつ)といいます。
1オクターブを12の半音に等分した音律を平均律(へいきんりつ)または十二平均律(じゅうにへいきんりつ)といいます。
また、楽音間の音程関係を正確に計算して定めた音律を純正律(じゅんせいりつ)または純正調(じゅんせいちょう)といいます。
Vol.3 譜表と音部記号
音の高低を示すために、5本の平行な横線を等間隔に引いたものを譜表(ふひょう)といいます。
5本の線が引かれていることから、五線譜(ごせんふ)ともいいます。
また、線と線の間を間(カン)といいます。
譜表には五線と四間(4つの間)があります。
譜表では音符のたまの位置によって音の高さを表します。
音符のたまは線の上、または間に書き表します。
五線と四間にはそれぞれ名前が付けられていて、下から上に向かって順に第一線、第二線…、また、第一間、第二間・・・、と呼びます。
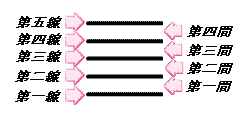
しかし、五線だけでは表せる音高が限られてきます。
それより高い音や低い音を表記する場合、まず、五線の上下の間を用いてあらわします。
さらに高い音や低い音を表すためには、あたらしく1本の線を書き加えます。
この書き加えた線を加線(かせん)といいます。
加線は必要なときにだけ書き加えるため、また五線と区別するために短くなっています。
また、五線の上下や加線と加線の間も音程を表すために用いることができ、これを加間(かかん)といいます。
これらの言いかたは、五線より高いか低いかによって「上」または「下」を付け、五線に近いほうから順に第一、第二・・・となります。
ですから、五線の上にある加線を五線に近いほうから順に上第一線、上第二線・・・、
また、五線の下にある加線を五線に近いほうから順に下第一線、下第二線・・・といいます。
同じように五線の上にある間を五線に近いほうから順に上第一間、上第二間・・・、
また、五線の下にある間を五線に近いほうから順に下第一間、下第二間・・・といいます。
上第一間、下第一間に音符を記入する場合、加線は用いません。
五線が引かれているだけでは、どの線がどの音の高さに対応しているのか決めることができません。
そこで音部記号(おんぶきごう)を用いて音の高さや音名を決めます。
音部記号は五線の左端にしるされ、
五線を下の方へ続けたりページを変えたりなどをする際には、そのたびに五線の左端にしるさなければなりません。
つまりは五線が一度とぎれたら、また音部記号を書かなければならないということです。
五線と音部記号とはいつも結合して音高を示しているため、これらを別々に切り離すと何の意味も持たなくなります。
このように、音部記号は譜表における音の高低を決めるために用いられます。
では、音部記号の種類を見ていってみましょう。
① ト音記号(高音部記号・バイオリン記号)
ト音記号は、ローマ字のGを変化させたもので、渦の中心(第二線)がGの音であることを表しています。
G<英名>=ト<日本名>なので、ト音記号と呼ばれます。
この場合のGは一点ト音を示します。
ト音記号は高音部記号やヴァイオリン記号とも呼ばれます。
ト音記号の付いた五線をト音譜表、または高音部譜表といいます。
ト音譜表の描き方は、第四線がト音であることをはっきりさせるために、第ニ線から描き始めて、
第ニ線のまわりをまわっていくように渦を作っていきます。
ト音記号によって一点ト音の位置が決められましたが、幹音は常に、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、イ、ロの順に並んでいるので、
ト音の位置が決定すれば、そのほかの幹音の位置も決定されてきます。

② ヘ音記号(低音部記号・バス記号)
ト音譜表の場合、非常に低い音を表すときに下方に加線が大量に必要になります。
この加線の数が多くなるほど記譜も読譜も困難になります。
そこで、低音部を中心に譜表を書き表すために、ヘ音譜表を用います。
ヘ音譜表では、ト音譜表で示すのに困難な低い音も簡単に表すことができます。
ヘ音記号は、ローマ字のFを変化させたもので、右の2点の間(第四線)がFの音であることを表しています。
F<英名>=ヘ<日本名>なので、ヘ音記号と呼ばれます。
この場合のFはカタカナヘ音を示します。
ヘ音記号は低音部記号やバス記号とも呼ばれます。
ヘ音記号の付いた五線をヘ音譜表、または低音部譜表といいます。
ヘ音記号の描き方は、第四線がへ音であることをはっきりさせるために第四線から描き始めて、
最後に第四線をはさんで2個の小さい点を打ちます。
ヘ音記号によって、カタカナヘ音の位置が決定したので、その他の音の位置は、これをもとに順々に定めることができます。
ヘ音記号を、第三線から描き始め、最後に第三線をはさんで2個の小さい点を打った場合、ヘ音の位置が第三線になります。
このときの譜表をバリトン譜表といい、この音部記号をバリトン記号といいます。
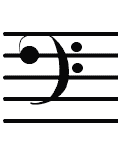
③ ハ音記号(アルト記号、ヴィオラ記号)
ほとんどの譜表は、ト音譜表、または、ヘ音譜表で書かれています。
ごくわずかですが、C<英名>=ハ<日本名>の位置を示したハ音記号を用いることがあります。
ハ音記号は、高音部譜表(ト音譜表)と低音部譜表(ヘ音譜表)の中間の高さを表すために用い、
主に合唱曲のアルト(女声の低音)でこれを用いた譜表を使用します。
ハ音記号は、第三線がセンターC(一点ハ音)の音であることを表しています。
ハ音記号はアルト記号やヴィオラ記号とも呼ばれます。
ハ音記号の付いた五線をアルト譜表といいます。
ハ音記号によって、センターCの位置が決定したので、その他の音の位置は、これをもとに順々に定めることができます。
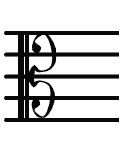
ハ音記号で、Cの位置を第四線に持ってきたものをテノール記号といい、この記号がついた譜表をテノール譜表と言います。
これは、おもに合唱曲のテノールの楽譜に使用します。
ハ音記号で、Cの位置を第一線に持ってきたものをソプラノ記号、またはディスカント記号といい、
この記号がついた譜表をソプラノ譜表、またはディスカント譜表と言います。
これは、おもに、合唱曲のソプラノの楽譜に使用します。
ハ音記号で、Cの位置を第ニ線に持ってきたものを、メゾソプラノ記号といい、この記号がついた譜表をメゾソプラノ譜表と言います。
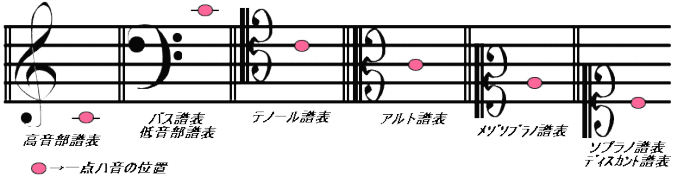
楽譜などを見てわかるように、譜表はひとつの五線譜がずっと続けて書かれているものだけではありません。
パート分けされていたりもしますね。
そして、それらが連結して、ひとつの譜表になっています。
① 大譜表
大譜表は高音部譜表を上段に、低音部譜表を下段にし、その中心にセンターCをもってきたもので、
左端を1本の縦線で結び、さらに括弧を付けてあらわします。
大譜表は、上下に1本ずつ加線を加えるだけでセンターCから上下2オクターブの音高を書き表す事が出来るので、
鍵盤楽器などの広い範囲の音程を使用する楽器に使われます。
鍵盤楽器では高音部を右手で、低音部を左手で弾きます。
② 連合譜表
伴奏用の譜表と独唱(独奏)用の譜表とを上下に結合したものを連合譜表(れんごうふひょう)と呼びます。
大譜表も総譜も、みな連合譜表の一種です。
連合譜表の中には譜表を3段にしたものも使用されます。
鍵盤楽器では、右手と左手の分担を区別させるため、そのうち一方の担当する2段の譜表を括弧で結びます。
また、足の鍵盤(ペダル)と手で弾く譜表を区別するために、手の鍵盤でひく方を括弧で結びます。
③ 総譜
楽曲において同時に演奏される全ての楽器の譜表を上下にかさねて、
さらに左端を縦線と括弧で結んだものを総譜(そうふ)といいます。
合唱などで多く用いられ、また、バンド譜などもこれにあたります。
スコア/score、またはパルティトゥーア/Partitureともいいます。
Vol.4 全音階的音程と半音階的音程
ある2つの音の高さの差(開き方)を音程(おんてい)といい、度(ど)という単位を用いて表します。
2つの音のうち、下の音をもとにして、上の音が何番目の音か数えます。
このとき、もととなる音を一度として数えるため、鍵盤ひとつ離れた音を二度、鍵盤二つ離れた音を三度と数えます。
一度音程はもととなる音とまったく同じ高さの音であることから、同音、同度、ユニソン/unisonともいいます。
八度音程には、もととなる音と同じ音名の音がきます。
八度音程のことをオクターブ/octaveともいいます。
一度から八度までの音程を単純音程(たんじゅんおんてい)、または、単音程(たんおんてい)といいます。
それに対し、八度よりも大きい音を複合音程(ふくごうおんてい)、または、複音程(ふくおんてい)といいます。
複音程の九度というのは、1オクターブ上の同じ音から見ると二度にあたります。
このため、複音程である九度を、単音程の直して、二度とかぞえる方法もあります。
同じようにして、他の複音程も単音程に直してかぞえることができます。
九度は二度、十度は三度、十一度は四度、十二度は五度、十三度は六度、十四度は七度になります。
① 全音階と半音階
譜表において、ある音からその1オクターブ上の音までの間に臨時記号を用いずに表すことが出来る音は、
もととなる音を含めて7つに限定されます。
このことは調号の有無にかかわらず一定で、隣り合うそれぞれの音が半音、または全音(1音)の音程の差を持っています。
これを実際にかぞえてみると、半音が2つと全音が5つあり、全音の方が圧倒的に多いことがわかるでしょう。
ですからオクターブのほとんどは全音で成り立っているといえます。
このため、1オクターブを7つの構成音に分けたものを
全音階(ぜんおんかい)、または全音階的音階(ぜんおんかいてきおんかい)といいます。
これに対し、1オクターブを12個の半音で分け、全音を含まないとしたものを
半音階(はんおんかい)、または半音階的音階(はんおんかいてきおんかい)といいます。
半音階は、全音階の7つの構成音にそれらの派生音を加えたものになります。(=クロマチックスケール)
② 全音階的半音と半音階的半音
半音には全音階的半音(ぜんおんかいてきはんおん)と半音階的半音(はんおんかいてきはんおん)の2種類が存在します。
全音階的半音とは、ある2つの音の音程間隔が二度の関係にある半音をいいます。
わかりやすく言うと、BとC、EとFのように、ある幹音とその隣りにある幹音との関係が半音のもの、
またはDとE♭、F#とGなどのようにある幹音と隣りにある幹音の派生音との関係が半音のものをいいます。
つまりは幹音名が異なり、半音の関係にあるもののことです。
幹音の名前が違うのですから、譜表において2つの音が同一の線上、または同一の間上にはないことになります。
全音階的半音は、調号を用いる事により臨時記号を用いずに半音を表すことができます。
これに対して半音階的半音とは、ある2つの音の音程間隔が一度の関係にある半音をいいます。
わかりやすく言うと、DとD♭、FとF#などのように、ある幹音とその幹音の派生音との関係をいいます。
つまりは幹音名が同じで半音の関係にあるもののことです。
幹音の名前が同じですから、譜表において2つの音が同一の線上、または同一の間上に存在することになります。
また、G♭とG
③ 半音階的変化音
幹音や派生音を、変化記号を用いて変化させた音を
半音階的変化音(はんおんかいてきへんかおん)、または変化音(へんかおん)といいます。
④ 全音階的音程と半音階的音程
全音階的音程(ぜんおんかいてきおんてい)は、全音階における7つの構成音と構成音の高さの差(開き方)を表したものです。
これに対し半音階的音程(はんおんかいてきおんてい)とは全音階的音程の構成音が半音階的に変化したもので、
全音階的音程に含まれないものをいいます。
ですから、半音階的音程とは半音階的変化音を含む音程であり、また、全音階的音程の派生音程でもあります。
⑤ 旋律的音程と和声的音程
2音が継続して鳴り響くとき、この音程を旋律的音程(せんりつてきおんてい)といいます。
これに対して、2音が同じに響くものを和声的音程(わせいてきおんてい)といいます。
Vol.5 全音階的音程
音程は、上下の2音の間にある全音と半音の数で、
完全音程(かんぜんおんてい)、長音程(ちょうおんてい)、短音程(たんおんてい)、
増音程(ぞうおんてい)、減音程(げんおんてい)の5種類に分類されています。
<一度音程>
全音階に存在する、全く同じ高さの2音は完全一度です。
<二度音程>
二度音程の中には、BとCのように2音の間に半音の音程差があるものと、
CとDのように全音の音程差があるものの2種類が存在します。
2音の間に半音の差があるものを短二度といい、全音の差があるものを長二度といいます。
<三度音程>
三度音程の中には、EとGのように2音の間に1つの全音と1つの半音の音程差があるものと、
CとEのように2つの全音の音程差があるものの2種類が存在します。
2音の間に1全音と1半音の差があるものを短三度といい、2全音の差があるものを長三度といいます。
<四度音程>
四度音程は、CとFのように2音の間に2つの全音と1つの半音の音程差があるものがほとんどです。
このため、2全音と1半音の差があるものを完全四度といいます。
ただし、FとBのように2音の間に3つの全音の音程差を持つものがあります。
2音の間に3全音の差がある音程は、完全四度よりも半音1つ分だけ増えた音程であるため、増四度といいます。
増四度は調号の種類に限らず全音階の1オクターブの中に1つだけ存在します。
増四度は、三全音(さんぜんおん)ともいいます。
<五度音程>
五度音程は、CとGのように2音の間に3つの全音と1つの半音の音程差があるものがほとんどです。
このため、3全音と1半音の差があるものを完全五度といいます。
ただし、BとFのように2音の間に2つの全音と2つの半音の音程差を持つものがあります。
2音の間に2全音と2半音の差がある音程は、完全五度よりも半音1つ分だけ減った音程であるため、減五度といいます。
減五度は調号の種類に限らず全音階の1オクターブの中に1つだけ存在します。
<六度音程>
六度音程の中には、AとFのように2音の間に3つの全音と2つの半音の音程差があるものと、
CとAのように4つの全音と1つの半音の音程差があるものの2種類が存在します。
2音の間に3全音と2半音の差があるものを短六度といい、4全音と1半音の差があるものを長六度といいます。
<七度音程>
七度音程の中には、AとGのように2音の間に4つの全音と2つの半音の音程差があるものと、
CとBのように5つの全音と1つの半音の音程差があるものの2種類が存在します。
2音の間に4全音と2半音の差があるものを短七度といい、5全音と1半音の差があるものを長七度といいます。
<八度音程>
ある音と、そのオクターブ音とで構成される2音は、5つの全音と2つの半音の音程差があり、完全八度といいます。
このようにして、2音の間に含まれる全音と半音の数で音程の名前が違い、それぞれの性質も違ってきます。
全音階的音程は、14種類の度数と性質の異なる音程が存在する事になります。
増四度と減五度は同じひびきの異名同音的音程となるため、実際には全音階的音程は13種類の音程を持つことになります。
調を変えても(どんな高さの音をもとにしても)同じように全音階的音程を構成することができ、
それぞれについて同じように、14種類(異名同音的音程を考慮すると13種類)の音程を持つことになります。
<全音階的音程の分類>
完全音程には、完全一度、完全四度、完全五度、完全八度の四つがあります。
二・三・六・七度は長音程と短音程にわけられます。
例外として、完全四度よりも半音多い増四度、完全五度よりも半音少ない減五度があります。
Vol.6 音程の変化
<基準音程の変化>
完全音程、長音程、短音程の3種類の音程を基準音程(きじゅんおんてい)といいます。
基準音程は、度ごとに完全音程になるものと、長音程または短音程になるものの2種類に分けられます。
一度、四度、五度、八度の基準音程は、かならず完全音程になり、これらが長音程や短音程になることはありません。
二度、三度、六度、七度の基準音程は、かならず長音程か短音程のどちらかになり、これらが完全音程になることはありません。
増音程と減音程は、基準音程に半音階的変化(音程を半音増やす、または減らす)を与えることにより
基準音程の性質が変わり、派生したものをいいます。
増音程は、基準音程(完全音程・長音程)よりも半音多いものをいいます。
また、減音程は基準音程(完全音程・短音程)よりも1半音少ないものをいいます。
増音程と減音程は、基準音程に半音階的変化を与えることにより派生するため、
増音程は基準音程(完全音程・長音程)に半音増やすことにより作ることができます。
また、減音程は基準音程(完全音程・短音程)から半音減らすことにより作ることができます。
短音程に半音増やすと長音程になり、長音程から半音減らすと短音程になります。
<一度、四度、五度、八度の音程変化>
| 減音程 | →(半音増やす)→ ←(半音減らす)← |
完全音程 | →(半音増やす)→ ←(半音減らす)← |
増音程 |
<二度、三度、六度、七度の音程変化>
| 減音程 | →(半音増やす)→ ←(半音減らす)← |
短音程 | →(半音増やす)→ ←(半音減らす)← |
長音程 | →(半音増やす)→ ←(半音減らす)← |
増音程 |
では、次は半音階的音程です。
半音階的音程とは全音階的音程の構成音が半音階的に変化したもので、全音階的音程に含まれないものをいいました。
このため、音程に半音階的変化を与えて半音階的音程を作ることができます。
<2つの音の差を半音大きくする方法>
2音のうち、上の音を半音上げる、または下の音を半音下げることにより、
もとの音程よりも半音1つ分だけ増えた音程を作ることができます。
これにより、完全音程と長音程は増音程に、短音程は長音程に、減音程は完全音程または短音程に変化します。
減音程から変化させる場合、1・4・5・8度の減音程は完全音程に変わり、2・3・6・7度の減音程は短音程に変わります。
たとえば、CとF(完全四度)の上の音であるFを半音上げてF#とすると、
完全四度の音程よりも半音1つ分だけ増えた音程になり増音程になります。
よって、CとF#は増四度となります。
また、下の音であるCを半音下げてC♭とすると、完全四度の音程よりも半音1つ分だけ増え増四度となります。
同様の方法で他の様々な半音階的音程を作ることができます。
| 完全音程・長音程 | →(2音の差を半音広げる)→ | 増音程 |
| 短音程 | →(2音の差を半音広げる)→ | 長音程 |
| 減音程 | →(2音の差を半音広げる)→ | 完全音程(1・4・5・8度の場合) |
| 短音程(2・3・6・7度の場合) | ||
<2つの音の差を半音小さくする方法>
2音のうち、上の音を半音下げる、または下の音を半音上げることにより、
もとの音程よりも半音1つ分だけ減った音程を作ることができます。
これにより、完全音程と短音程は減音程に、長音程は短音程に、増音程は完全音程または長音程に変化します。
増音程から変化させる場合、1・4・5・8度の増音程は完全音程に変わり、2・3・6・7度の増音程は長音程に変わります。
たとえば、AとC(短三度)の上の音であるCを半音下げてC♭とすると、
短三度の音程よりも半音1つ分だけ減った音程になり減音程になります。
よって、AとC♭は減三度となります。
また、下の音であるAを半音上げてA#とすると、短三度の音程よりも半音1つ分だけ減り減三度となります。
同様の方法で他の様々な半音階的音程を作ることができます。
| 完全音程・短音程 | →(2音の差を半音小さくする)→ | 減音程 |
| 長音程 | →(2音の差を半音小さくする)→ | 短音程 |
| 増音程 | →(2音の差を半音小さくする)→ | 完全音程(1・4・5・8度の場合) |
| 長音程(2・3・6・7度の場合) | ||
<2つの音の差を半音2つ分だけ大きくする方法>
2音のうち、上の音を半音上げて下の音を半音下げる、または上の音を半音2つ分上げる、
または下の音を半音2つ分下げることにより、もとの音程よりも半音2つ分増えた音程を作ることができます。
これにより減音程は長音程または増音程に、短音程は増音程に変化します。
減音程から変化させる場合、1・4・5・8度の減音程は増音程に変わり、2・3・6・7度の減音程は長音程に変わります。
たとえば、BとF(減五度)の上の音であるFを2半音上げてF
減五度の音程よりも半音2つ分だけ増えた音程になり増音程になります。
よって、BとF
また、同様の2音を用いて、上の音を半音上げるとともに下の音を半音下げたB♭とF#、
または下の音を半音2つ分下げたB
同様の方法で他の様々な半音階的音程を作ることができます。
| 短音程 | →(2音の差を半音2つぶん広げる)→ | 増音程 |
| 減音程 | →(2音の差を半音2つぶん広げる)→ | 増音程(1・4・5・8度の場合) |
| 長音程(2・3・6・7度の場合) | ||
<2つの音の差を半音2つ分だけ小さくする方法>
2音のうち、上の音を半音下げて下の音を半音上げる、または上の音を半音2つ分下げる、
または下の音を半音2つ分上げることにより、もとの音程よりも半音2つ分減った音程を作ることができます。
これにより増音程は短音程または減音程に、長音程は減音程に変化します。
増音程から変化させる場合、1・4・5・8度の増音程は減音程に変わり、2・3・6・7度の増音程は短音程に変わります。
たとえば、FとB(増四度)の上の音であるBを2半音下げてB
増四度の音程よりも半音2つ分だけ減った音程になり減音程になります。
よって、FとB
また、同様の2音を用いて、上の音を半音下げるとともに下の音を半音上げたF#とB♭、
または下の音を半音2つ分上げたF
同様の方法で他の様々な半音階的音程を作ることができます。
| 長音程 | →(2音の差を半音2つぶん小さくする)→ | 減音程 |
| 増音程 | →(2音の差を半音2つぶん小さくする)→ | 減音程(1・4・5・8度の場合) |
| 短音程(2・3・6・7度の場合) | ||
これらの方法によって、全音階的音程に追加された
増一度・減二度・増二度・減三度・増三度・減四度・増五度・減六度・増六度・減七度・増七度・減八度が
半音階的音程になります。
Vol.7 転回音程
次は2つの音自体を変えずに、性質を変化させる方法です。
音程を形成している2音のうち、下の音を上方のオクターブに移すことができ、
また、上の音を下方のオクターブに移すこともできます。
このように、一方をオクターブ音に移すことを転回(てんかい)といいます。
そして、音程を転回することによってできた音程を転回音程(てんかいおんてい)といいます。
たとえば、AとC(短三度)の2音の場合、
下のAの音を1オクターブ上のAの音に転回することにより、Aが上の音になり、Cが下の音になります。
したがって、AとC(短三度)だったものが、転回によりCとA(長六度)になります。
また、AとC(短三度)の2音のうち、上のCの音を1オクターブ下のCの音に転回することによっても音の上下が入れ替わり、
CとA(長六度)になります。
このように、音程を転回すればその度数と性質が変わってきます。
転回音程の度数は、9からもとの音程の度数を差し引いたものになります。
<転回による度数の変化>
| 二度⇔七度 |
| 三度⇔六度 |
| 四度⇔五度 |
音程を転回すると、度数だけではなく、その性質も変わってきます。
ただし、完全音程だけは性質が変わりません。
<転回による性質の変化>
| 完全音程⇔完全音程 |
| 長音程⇔短音程 |
| 増音程⇔減音程 |
Vol.8 装飾音
旋律の音を本音(ほんおん)といい、旋律を飾る為にもちいられる音を副音(ふくおん)といいます。
副音は装飾する音であることから、一般には装飾音(そうしょくおん)と言われています。
装飾音を表すために装飾記号や、音符のサイズを小さくした装飾音符を使います。
副音のうち本音と2度はなれた音程にあるものを補助音といいます。
① 前打音
前打音(ぜんだおん)は本音の前にすべりこませる副音で、本音の前に小音符(サイズを小さくした音符)を書いて表します。
演奏では小音符で記載された通りの長さを演奏します。
そのために、その直後の本音は記載された歴時よりも前打音の長さのぶんだけ短い長さになります。
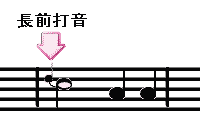 |
長前打音(ちょうぜんだおん)は本音の半分の長さになります。 本音が付点音符の場合には、3分の1または3分の2の長さになります。 長前打音は本音と比べて二度上または二度下の補助音でなければなりません。 長前打音にはアクセントをつけます。 |
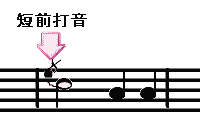 |
短前打音(たんぜんだおん)は小音符に斜線をつけて表します。 通常は八分音符の長さになります。 音程は本音と比べて二度でなくても可能です。 短前打音にアクセントはなく、本音にアクセントをつけます。 |
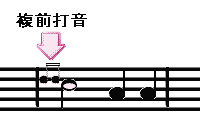 |
複前打音(ふくぜんだおん)は前打音が複数個ついたもので、 通常は16分音符または32分音符が連なります。 音程は本音と比べて二度でなくても可能です。 また、連なる二音の音程が異なってもかまいません。 複前打音にアクセントはなく、本音にアクセントをつけます。 複前打音が三度下、続いて二度下などの順にならんでいて、 順に本音の音程に近づき本音にすべりこむものを 滑奏音(かっそうおん)<Schleifer/シュライファー>といいます。 |
② 後打音
後打音(こうだおん)は本音の後つけ加えられる副音で、本音が終わる直前に発音し、すぐに次の音にすべりこみます。
本音の後に小音符を書いて表します。
演奏では小音符で記載された通りの長さを演奏します。
そのため、その直前の本音は記載された歴時よりも後打音の長さのぶんだけ短い長さになります。
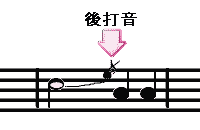
後打音は本音と比べて二度音程でなくても構いません。
後打音が複数個ついたものを複後打音(ふくこうだおん)といいます。
では、これらの前打音、後打音を応用した装飾記号を紹介します。
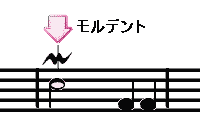 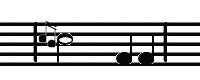 |
モルデント/Mordentは本音の前に、本音と同じ音、二度下の音の順で 急速に発音するという意味があります。 複前打音の表記方法で全く同じことを表すこともできます。 アクセントの位置は複前打音で表記されたときの本音の位置になります。 |
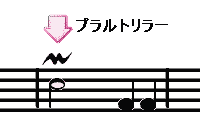 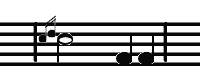 |
プラルトリラー/Pralltrillerは本音の前に、本音と同じ音、二度上の音の順で 急速に発音するという意味があります。 複前打音の表記方法で全く同じことを表すこともできます。 アクセントの位置は複前打音で表記されたときの本音の位置になります。 |
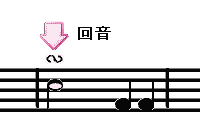 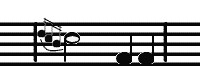 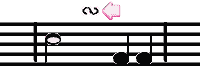 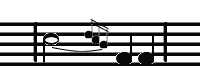 |
回音(かいおん)、(またはターン/turnともいう)は、 二度上の音、本音と同じ音、二度下の音の順で急速に発音するという意味があります。 <音符の真上に回音記号がある場合> 本音の直前に二度上の音、本音と同じ音、二度下の音の順で急速に発音します。 複前打音の表記方法で全く同じことを表すこともできます。 アクセントの位置は複前打音で表記されたときの本音の位置になります。 <音符の真上よりも右側の方に回音記号がある場合> 本音が終わる直前に二度上の音、本音と同じ音、二度下の音の順で発音し、 すぐに次の音にすべりこみます。 複後打音の表記方法で全く同じことを表すこともできます。 <転回ターン> 回音と逆の順序(二度下の音、本音と同じ音、二度上の音の順)で急速に発音するとき 転回ターン(てんかいターン)、または逆回音(ぎゃくかいおん)といいます。 転回ターンの場合、特別な記号は用いずに、複前打音や複後打音で表記します。 アクセントの位置は本音と同じ位置になります。 |
他にも装飾音があります。
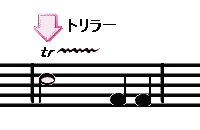 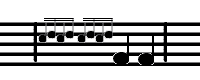 |
トリラー/Triller(またはトリル/trillともいう)は、 本音と、その二度上の補助音とを、交互に急速に繰り返すことを意味しています。 下側の譜面のように書き換えることができます。 <トリラーの発音順序の並び替え> 前打音を入れることにより発音順序を並び替えることができます。 例えば前打音で二度上の音を16分音符で入れたとすると、 最初が二度上の音、残りの音がトリラーにより本音、二度上を繰り返すため、 二度上の音、本音の順番で、交互に繰り返すことになります。 同じようにモルデント、プラルトリラー、ターンをトリラーと組み合わせて 順序を替えることもできます。 |
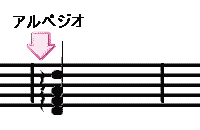  |
アルペジオ/arpeggioは和音の音を同時にではなく、 ほんの少しずつずらして発音するという意味があります。 分散和音(ぶんさんわおん)を意味します。 ただし、音を消すタイミングは同時になります。 |
Vol.9 長音階の種類
音階(おんかい)とは、旋律や和音に用いられる音を音高の順にならべたものをいいます。
音階の出発点の音を主音(しゅおん)といい、そこからオクターブ上の同じ音名の音までの各音を並べたものが音階になります。
音階は、音階音(音階を組み立てる音)と、その並び方によって様々な特色があります。
主音の三度上の音階音が長三度であれば長音階、短三度であれば短音階になります。
<各国の音階の呼び方>
| 長音階 | 短音階 | ||
| 日本 | 記述 | 長調 | 短調 |
| 米・英 | 記述 | major | minor |
| 読み方 | メジャー | マイナー | |
| ドイツ | 記述 | dur | moll |
| 読み方 | ドゥア | モル | |
| フランス | 記述 | majeur | mineur |
| 読み方 | マジュール | ミニュール | |
| イタリア | 記述 | maggiore | minore |
| 読み方 | マジョーレ | ミノーレ | |
<長音階と構成音>
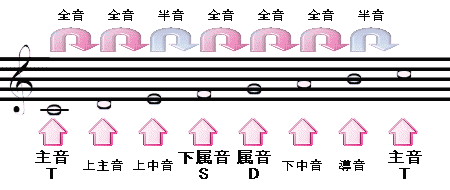
| 第一音 | 主音(しゅおん) tonic(トニック) |
音階の出発点で、tonicの頭文字をとってTで表します。 音階の名前(調名)は、主音の音高で決められます。 |
| 第二音 | 上主音(じょうしゅおん) | 主音のすぐ上の音をいいます。 |
| 第三音 | 上下音(じょうちゅうおん) | 主音の三度上の音(長三度)をいいます。 |
| 第四音 | 下属音(かぞくおん) subdominant(サブドミナント) |
完全四度の音を下属音といいます。 subdominantの頭文字をとってSで表します。 |
| 第五音 | 属音(ぞくおん) dominant(ドミナント) |
完全五度の音を属音といいます。 dominantの頭文字をとってDで表します。 |
| 第六音 | 下中音(かちゅうおん) | 下属音と主音(オクターブ)との中間の音をいいます。 |
| 第七音 | 導音(どうおん) | 主音(オクターブ)の半音下の音をいいます。 |
<テトラコード>
長音階を半分に切ったとき、下の図のように4音ずつの上下2組の音列にわけることができ、
この音列をtetrachord/テトラコード、四声音列(しせいおんれつ)といいます。
上下二つの音列ともに、全音-全音-半音の順序でならんでいます。
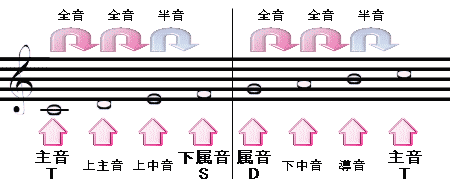
① 嬰種長音階
主音をC(ド)以外の音にした場合、長音階を表すためには派生音が必要になります。
例えばG(ソ)を主音にした場合の例をあげます。
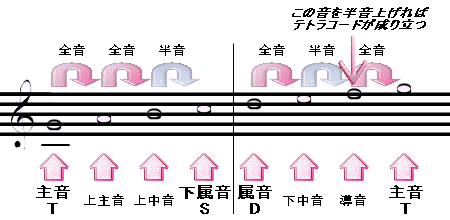
F(ファ)の音を半音上げて長音階を作ります。
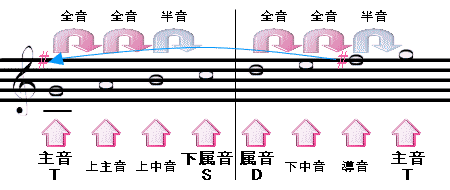
半音上げるためにつけた♯は、音符の前にある状態ならば臨時記号にを意味するので、
必要なたびに記載しなければならなくなります。
そのため、♯を音部記号のすぐ隣までもってきて譜表全体に影響させるようにします。
音部記号のすぐ隣のシャープは調の特徴を表すため、調号(ちょうごう)といいます。
また、音階または調の呼び名を調名(ちょうめい)といいます。
ある音を半音上げる(♯をつける)ことによって作られた長音階を嬰種長音階(えいしゅちょうおんかい)といいます。
② 変種長音階
F(ファ)を主音にした場合の例をあげてみます。
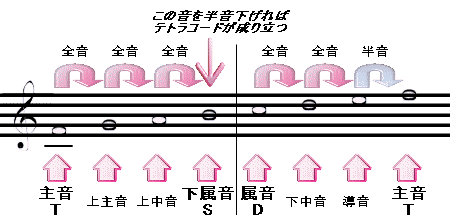
B(シ)の音を半音下げて長音階を作ります。
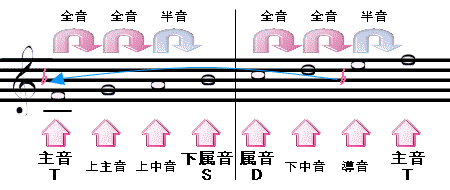
半音下げるためにつけた♭は、音符の前にある状態ならば臨時記号にを意味するので、
必要なたびに記載しなければならなくなります。
そのため、♭を音部記号のすぐ隣までもってきて譜表全体に影響させるようにします。
音部記号のすぐ隣のフラットは調の特徴を表すため、調号(ちょうごう)といいます。
また、音階または調の呼び名を調名(ちょうめい)といいます。
ある音を半音下げる(♭をつける)ことによって作られた長音階を変種長音階(へんしゅちょうおんかい)といいます。
③ 純長音階(純長調)
基準長音階、嬰種長音階、変種長音階は主音が異なるだけで、音階の並び方は全て同じになっています。
これらの音階を純長音階といいます。
④ 和声長音階(和声長調)
第六音を半音下げた長音階を和声長音階(わせいちょうおんかい)または、Molldur/モルドゥアといいます。
和声長音階では、サブドミナントだけ、゜S(まるS)で書き表します。
変化した第六音は、その二度下のドミナントに対してはたらく導音になり、
このように音高の低い音にはたらく導音を下行性導音(かこうせいどうおん)といいます。
これとは逆に、長音階の第七音のように音高の高い音にはたらく導音を上行性導音(じょうこうせいどうおん)といいます。
和声長音階は半音を3個持つため、やわらかいイメージになります。
ですが、増二度の音高差の場所もあるため歌いにくくなります。
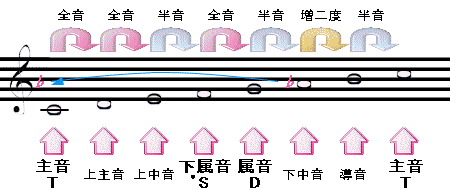
⑤ 旋律長音階(旋律長調)
和声長音階では、第六音と第七音が増二度で歌いにくいため、
第七音を半音下げて長二度にしたものを旋律長音階といいます。
この音階では、ドミナントとサブドミナントを、゜D(まるD)、゜S(まるS)で表記します。
旋律長音階では上行性導音が全音の音高差になってしまうため、上行には向きません。
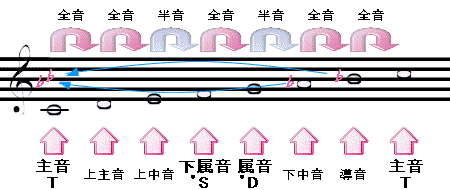
和声長音階や旋律長音階では、音階を特徴づける音を必要に応じて入れていきます。
特徴音(とくちょうおん)は、そのたびに臨時記号をつけて表します。
Vol.10 短音階の種類
<短音階と構成音>
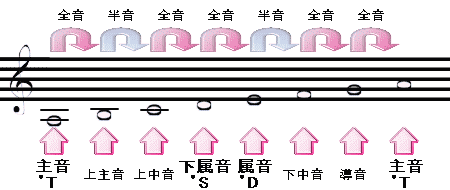
| 第一音 | 主音(しゅおん) tonic(トニック) |
長音階と区別して、゜Tで表記し、まるTと呼びます。 音階の名前(調名)は、主音の音高で決められます。 |
| 第二音 | 上主音(じょうしゅおん) | 主音のすぐ上の音をいいます。 |
| 第三音 | 上下音(じょうちゅうおん) | 主音の三度上の音(短三度)をいいます。 |
| 第四音 | 下属音(かぞくおん) subdominant(サブドミナント) |
完全四度の音を下属音といいます。 長音階と区別して、゜Sで表記し、まるSと呼びます。 |
| 第五音 | 属音(ぞくおん) dominant(ドミナント) |
完全五度の音を属音といいます。 長音階と区別して、゜Dで表記し、まるDと呼びます。 |
| 第六音 | 下中音(かちゅうおん) | 下属音と主音(オクターブ)との中間の音をいいます。 |
| 第七音 | 導音(どうおん) | 主音(オクターブ)の全音下の音をいいます。 |
① 自然短音階(自然短調)
短音階の基本的な配列に沿ったものを自然短音階、純短音階といいます。
C(ハ長調)とAm(イ短調)は全く同じ音階音を持ち、調号も全く同じになります。
このように、全く同じ音階音を用いる長音階と短音階を平行調(へいこうちょう)、または関係調(かんけいちょう)といいます。
A(イ長調)とAm(イ短調)などのように、同じ音高の主音で始まる長音階と短音階を
同名調(どうめいちょう)、または同主調(どうしゅちょう)といいます。
自然短音階の第三音を半音上げると旋律長音階と全く同じ音階音になります。
② 和声短音階(和声短調)
第七音を半音上げた短音階を和声短音階(わせいたんおんかい)といいます。
この音階では、ドミナントだけ、Dで表記します。
変化した第七音(導音)は、その二度上のトニックに対して半音の音高差になり、機能しやすくなります。
和声短音階は導音が半音になったため、トニックに向かって上行しやすくなります。
一方、増二度の音高差の場所もあるため、歌いにくくなります。
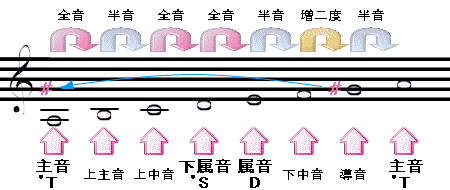
③ 旋律短音階(旋律短調)
和声短音階では、第六音と第七音が増二度で歌いにくいため、
第六音を半音上げて長二度にしたものを旋律短音階といいます。
この音階では、ドミナントとサブドミナントを、D、Sで表記します。
旋律長音階では下行性導音が全音の音高差になってしまうため、下行には向きません。
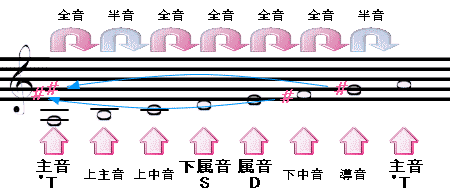
Vol.11 特殊な音階
① 全音音階
1オクターブを全音だけで6等分した音階を全音音階(ぜんおんおんかい)といいます。

② 半音階
1オクターブを12等分した全ての半音を音階音とした音階を半音階(はんおんかい)、クロマチックスケールといいます。
国や地域によって独自の音階もあります。
③ スコットランドの音階
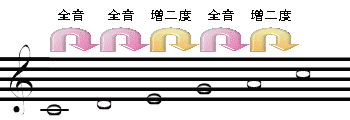
④ 琉球の音階
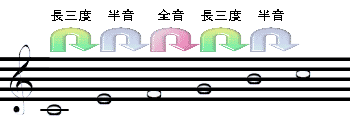
スコットランドの音階や、琉球の音階は、5つの音階音で構成されているため、5音音階といいます。
Vol.12 移調と転調
ある調の楽曲をそのまま他の調に移しかえることを移調(いちょう)と言います。
結果的に、全く同じ演奏が音の高さだけを変えてなされることになります。
それに対し、転調(てんちょう)は、ある調が他の調にかわり、新しい調で新しい演奏をすることになります。
転調する前の調を基調(きちょう)、または原調(げんちょう)といい、転調された後の調を新調(しんちょう)といいます。
Vol.13 教会旋法
<教会旋法(教会調)>
教会旋法(きょうかいせんぽう)は基準長音階の音程音をならべたものが、
どの音高の音から始まる音階かを定義したものです。
モードとも呼ばれています。
<イオニアン>
基準長音階の音程音をならべたものに、C(ド)を第一音(トニック)と定め、順に第二音、第三音・・・としていったもの。
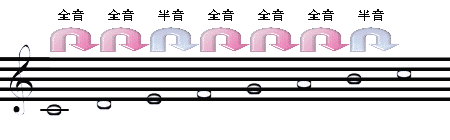
<ドリアン>
基準長音階の音程音をならべたものに、D(レ)を第一音(トニック)と定め、順に第二音、第三音・・・としていったもの。
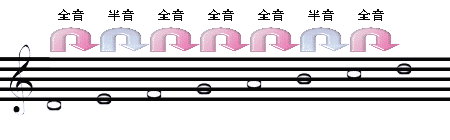
<フリジアン>
基準長音階の音程音をならべたものに、E(ミ)を第一音(トニック)と定め、順に第二音、第三音・・・としていったもの。
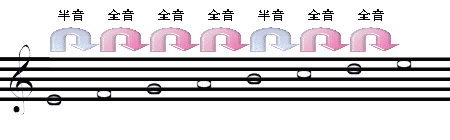
<リディアン>
基準長音階の音程音をならべたものに、F(ファ)を第一音(トニック)と定め、順に第二音、第三音・・・としていったもの。
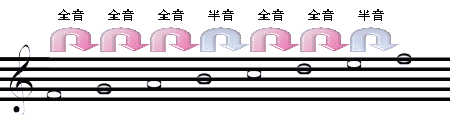
<ミクソリディアン>
基準長音階の音程音をならべたものに、G(ソ)を第一音(トニック)と定め、順に第二音、第三音・・・としていったもの。
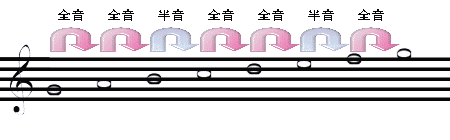
<エオリアン>
基準長音階の音程音をならべたものに、A(ラ)を第一音(トニック)と定め、順に第二音、第三音・・・としていったもの。
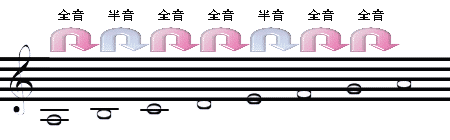
<ロクリアン>
基準長音階の音程音をならべたものに、B(シ)を第一音(トニック)と定め、順に第二音、第三音・・・としていったもの。
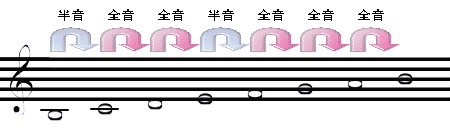
これらを、主音をそろえて並び替えてみましょう。
それぞれのモードの主音をC(ド)の音にしてみると、次の様になります。
<イオニアン>
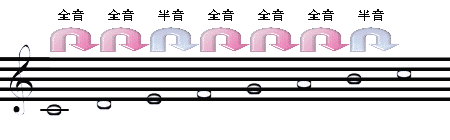
<ドリアン>
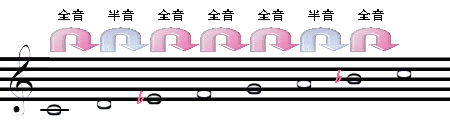
<フリジアン>
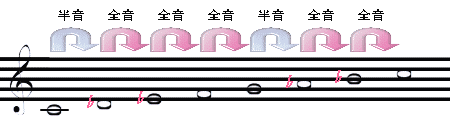
<リディアン>

<ミクソリディアン>
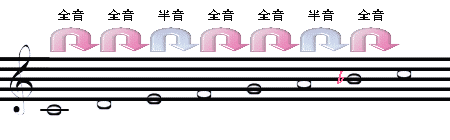
<エオリアン>
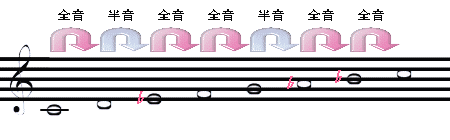
<ロクリアン>